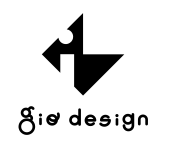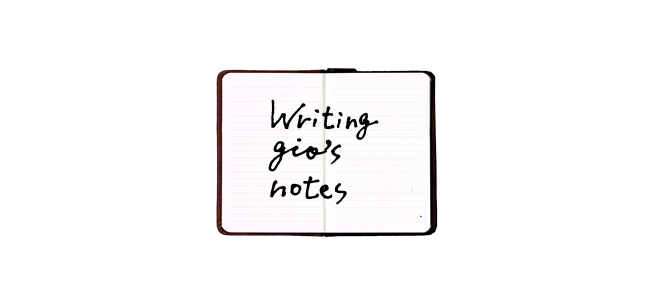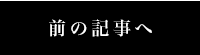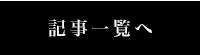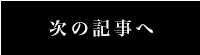お惣菜の食品ラベルを見て、ふと感じた“食の信用”のこと
先日、スーパーでお弁当を買おうとしたときのこと。
ふと、お惣菜の食品表示ラベルを見たら、以前は国産だった鶏肉や豚肉が知らないうちに海外産に変わっていました。
でも、値段は変わらず。
たぶん、仕入れの都合や価格調整の影響なんでしょうけど、それを“知らずに”買っている人もいると思います。
中には、国産だからという理由でそれを選んでいた人もいるかもしれない。
そう考えると、「気づかないうちに選んでいたものが変わっている」という事実に、ちょっとした違和感を覚えました。
周囲を見てみると、意外と多くの人がラベル表示をじっと見ていて、
「みんな“食べるものの情報”をちゃんと見ているんだな」と実感しました。
飲食店も「表示」が必要な時代?
こういう時代の流れを考えると、飲食店もこれからは“何を使っているか”を
ある程度オープンにしていく必要があるのではと感じました。
「ウチは国産しか使ってません!」というような主張でなくてもいい。
たとえば、
野菜の産地・肉や魚の仕入れ先・調味料や米のこだわり
そういう情報を少しだけでも伝えるだけで、“お店の姿勢”や“顔の見える感じ”が出てくる。
それはブランディングのためだけでなく、お客さんとの信頼関係を築く手段にもなるんじゃないでしょうか。
そういう小さなところが、“このお店いいな”につながる
価格や雰囲気、立地だけではなく「どんな材料を使って、どんなふうに出しているか」という部分が、
今後もっと重要になってくるように思います。
「どこで何を食べるか」よりも、「誰がどういう想いで作っているか」が問われる時代。
食品ラベルから始まったちょっと気になることでしたが、
見えない部分こそ、実はお客さんが一番気にしているのかもしれません。
空間も料理も、「選ばれる理由」はきっとそういう“しっかり見ている人”に届いていく。
そんなふうに感じた出来事でした。